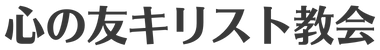再びイスタンブールへ
或る抜けるような青天の午後、通称THY (Turk Hava Yollari、トルコ航空)機は満員の乗客を乗せてアンカラ国際空港をイスタンプール国際空港へ向けて離陸した。間もなくアナトリア大地の畑や遠くに羊飼いと羊の群れが見え、その向こうには広大な大地が広がって見えた。真下には搭乗機の影が大地を這うように追っかけて来る。しかし、それは徐々に小さくなり眼下から消えた。
このルートをバスで走ると7時間半かかる。筆者は初め鉄道で行くことを試みた。アナトリアの大地をこの目で確かめたかったからである。しかし、いろいろ問い合わせてみても何時に発車してイスタンプールに何時に着くのか皆目見当もっかない。渋々この計画を断念することにした。
機上で目の前にあるイズミールやミトレス、トロイや大伝道者パウロに縁の地すなわちエーゲ海沿岸地方のパンフレットとフェティエやアンタルヤのある地中海沿岸のそれを見ながら次回の旅に思いを馳せていたら、いつの間にかまどろみへと誘われてしまったらしい。突き上げる衝撃に目が覚めた時にはもうイスタンプール空港に着いていた。約1時間のフライトであった。
空港では国内便であったこともあって手続きは簡単であった。入口、出口の到る所に緑色の制服を着た警察官(兵士? )が立っていて、なんとなく物々しいのも日本から入国した時には気付かなかったことである。ただ空港ではアナウンスの前に必ず3つの音からなるチャイムが鳴るのが妙に懐かしく聞こえたものだ。それは、 3音目の半音の響きに特徴があり、近くにいたドイツやオランダからの旅行者はその響きを聞いてヨーロッパからアジアに来たんだという思いを強くするのだそうだ。
イスタンプールはアンカラやカッパドキアとは違い、その日も人々が行き交い賑やかだった。車の往来は思った以上に激しく、その車の間をぬって道を横断する姿は真に離れ業としか言いようがない。しかも老若男女を問わずにそれをやるのだ。昔読んだ書物に作家が「この国では、町へ出れば自分の命を守るのは信号でも法律でもない。自分自身なのだ。」と書いていたのを思い起こしていた。この後、数日滞在し塩野七生の『コンスタンティノープルの陥落』(新潮社)を読み直してこの旅の終わりにすることとしていた。
通訳フールヤさん
今回のトルコの旅を顧みる時、一番の感謝はなんといっても通訳をしてくれたフールヤさんである。
夫君はイスタンプール大学で社会学を講じている。フールヤさんは20代に留学生として東京の下町に住み、日本語をまったく解さないまま「隣のおばあちゃん」に日本語を習い、ほぼ完璧な日本語を話す。その用語は、生活用語、学術用語、芸術用語、医学用語まで流暢にこなす。
私たちが訪れた時、彼女は30代の初めであったが、生まれたばかりの坊やを夫君の母親に預けて、数週間同道してくれた。夜、我々が宿舎に入ると「べービーの顔を見てくる」と帰宅し、翌朝朝食前にはホテルに戻っているのである。アンカラからカッパドキアに出かけた時は四六時中ついていてくれた。筆者はこのトルコ訪問に際して、筆者の学生やOB を7 ~ 8名連れて行った。フールヤさんはそのグループを「楽しい、楽しいグループ」と言ってくださり「もしまたどこかへ出かけるならトルコから出来る限り現地へ駆けつけるから呼んでください」とも言ってくれた。光栄なことである。
さて、トルコではどうして四六時中通訳が必要なのか。トルコ語以外通じないからである。イスタンプールやアンカラの空港、空港内の銀行出張所、大きなホテル以外で英語は何の役にも立たない。ましてや、地方に至ってはどうしようもない状態に陥る。イスタンプール大学の学生が履修する外国語で圧倒的に多いのはフランス語と聞いた。同大の教授によると博士号を取得する場合は、これまた圧倒的にフランスの大学からのものが多いそうだ。因みにフールヤさんのご夫君もパリ大学の博士号を持っているそうだ。歴史的な歩みの結果かどうかは別として英米は人気がないのである。ある田舎のレストランに昼食で立ち寄った時、立派な髭を蓄えた老人が見事なドイツ語で話しかけてきたのには驚いた。これもトルコが帝政ドイツとの関わりがあった
とを物語っているのか。
日本語は人気のある外国語らしい。絨毯の店でも立派な日本語で話しかけられた。初代大統領ケマル・アタチュルコはまだ日本との国交が出来る前に士官学校で日本語を学び、トルコと日本の国交が樹立されて日本国の初代トルコ大使が大統領にアグレマン(特定の人を外交使節に任命するに先立って、派遣する相手国が与える同意の意思表示)を提出した時、大統領は大使に日本語で話しかけられ周囲を驚かせたという逸話が残っている。以来、日本語は隠れたる外国語となっているらしい。それもトルコの人々が本質的に日本が好きということからなっている。それは、日本人の経済的援助の仕方、靴を脱いで家の中に入る習慣を好ましく思っている点など、日本人の礼儀正しさに共感する彼らの裏づけがあってのことだろう。こういう国民と友人関係である必要は大である。
フールヤさんが言うには、日本語とトルコ語はすこぶる似ているそうだ。そうならいつかトルコ語を学んで再度訪問したいものだ。新しいやる気が出てくるのを禁じえない私であった。
(今回をもって、「聖書の周辺世界を旅する『トルコ』」は終了です。愛読ありがとうございました。)